マルチビタミンと聞くと、大抵はサプリメントをイメージすることでしょう。
手軽に不足している栄養素を補う手段として、サプリメントはかなり重宝しますよね。
今では健康食品が身近になったこともあり、多くの人がサプリを利用しています。
さて、その中でも多くの人が利用しているマルチビタミンですが、処方薬としてのマルチビタミンもあることをご存知でしょうか。
ここでは、処方薬としてのマルチビタミンについて見ていきたいと思います。
処方薬は病気の治療が大前提
まず忘れてはならないのは、処方薬は病気の治療が大前提である、ということ。
たとえマルチビタミン(ビタミンB2製剤など)であっても、その処方薬としての基本的な概念は変わりません。
そのため処方薬としてのマルチビタミンは、ビタミンB2欠乏による症状を改善するためなど、「治療の一貫」てして処方されるわけです。
風邪のときに病院で風邪薬を処方されるのと、同じなんですよ。
ビタミンB2の場合は、エネルギー代謝や新陳代謝を促進する働きがあるため皮膚や粘膜、髪の毛などを健康に保つ働きが期待できます。
特に女性は美容のためにマルチビタミンを飲んでいる人もいますが、病気でないなら処方薬としてのマルチビタミンを飲むのはやめましょう。
処方薬としてのマルチビタミンは、健康な人が飲むと「ビタミンの摂りすぎ」になってしまう恐れもあるのです。
処方薬はあくまでも病気の人のみ、ということを、常に頭に入れておいてくださいね。
まとめ
処方薬としてのマルチビタミンについて、お話ししました。
私たちがイメージするマルチビタミンはサプリですが、処方薬としてのマルチビタミンもあります。
しかし処方薬は、一般の人が手に入れられるものではありません。
薬には副作用もありますし、一般の人は処方薬ではなくサプリのマルチビタミンを摂取するようにしてください。


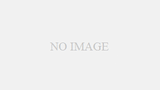
コメント